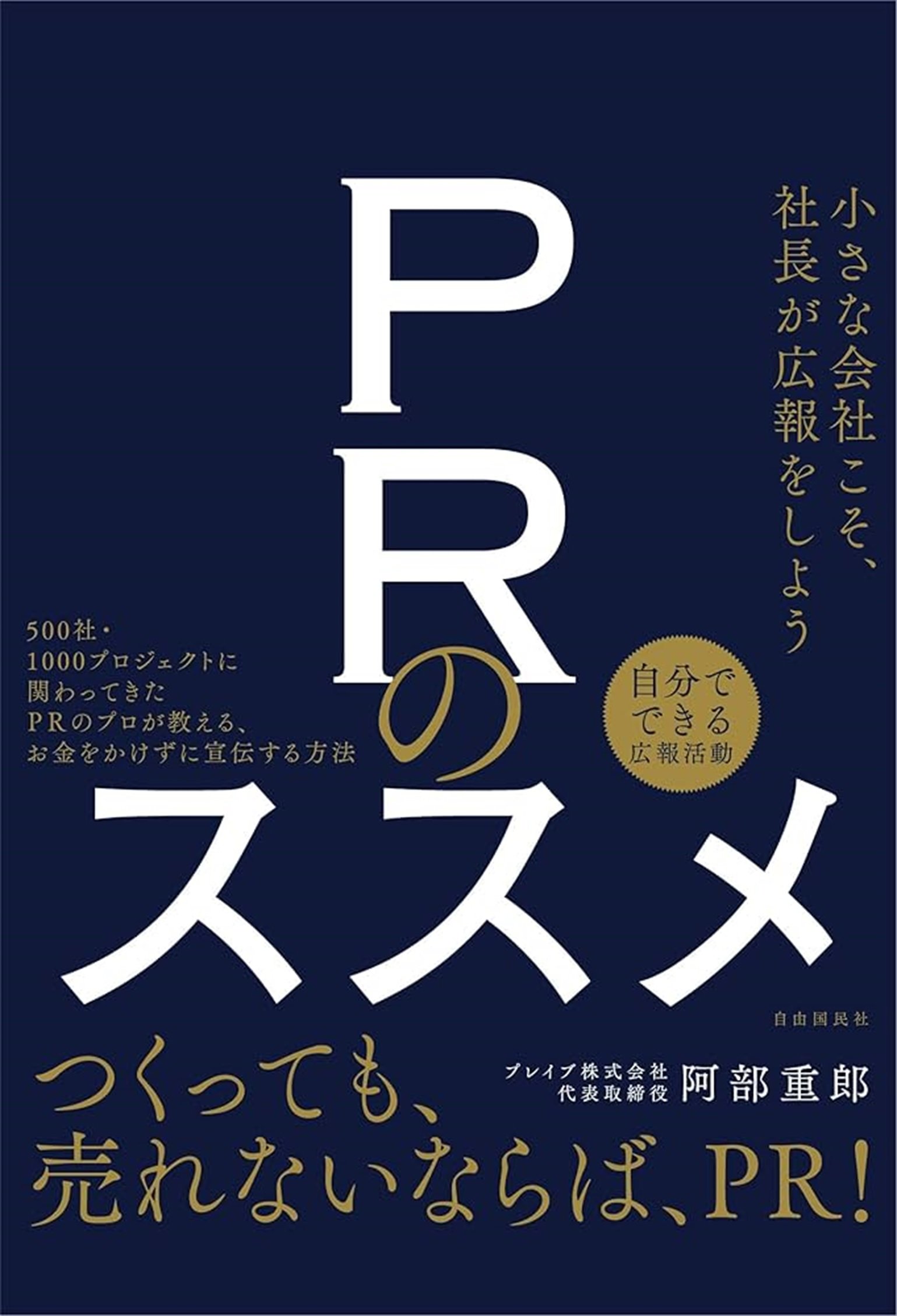鳥取市青谷町吉川の青谷かみじち史跡公園で9日、青谷上寺地遺跡で出土したイヌの骨から、弥生人とともに暮らした「弥生犬」を研究する催しがあった。古代史や研究職などに興味のある小学5年生から高校1年生の4人が、骨を手がかりに約2千年前の弥生犬の大きさや姿に思いを巡らせた。
参加者は出土したイヌの前足と後ろ足の骨の大きさを計測する作業に取り組み、ノギスで測った長さや幅の数値を基に骨を小級、中小級、中級に分類したほか、イヌの大きさの傾向を出土する時期区分(弥生時代前、中、後期、古墳時代)で調べてまとめ上げた。研究成果は春頃にインターネット上で発行する「青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報2024」に掲載する。
同遺跡では80体以上の犬の骨が見つかっており、全国でもトップクラスの出土量を誇る。同公園の門脇隆志文化財主事(44)は「人間がオオカミを飼いならしたのがイヌ。イヌを調べることで人間についても分かる」と話し、研究の重要性を訴えた。
鳥取市内の北川紗理さん(12)は「骨の測り方が最初は難しかったけど、慣れるととても面白かった」と話した。