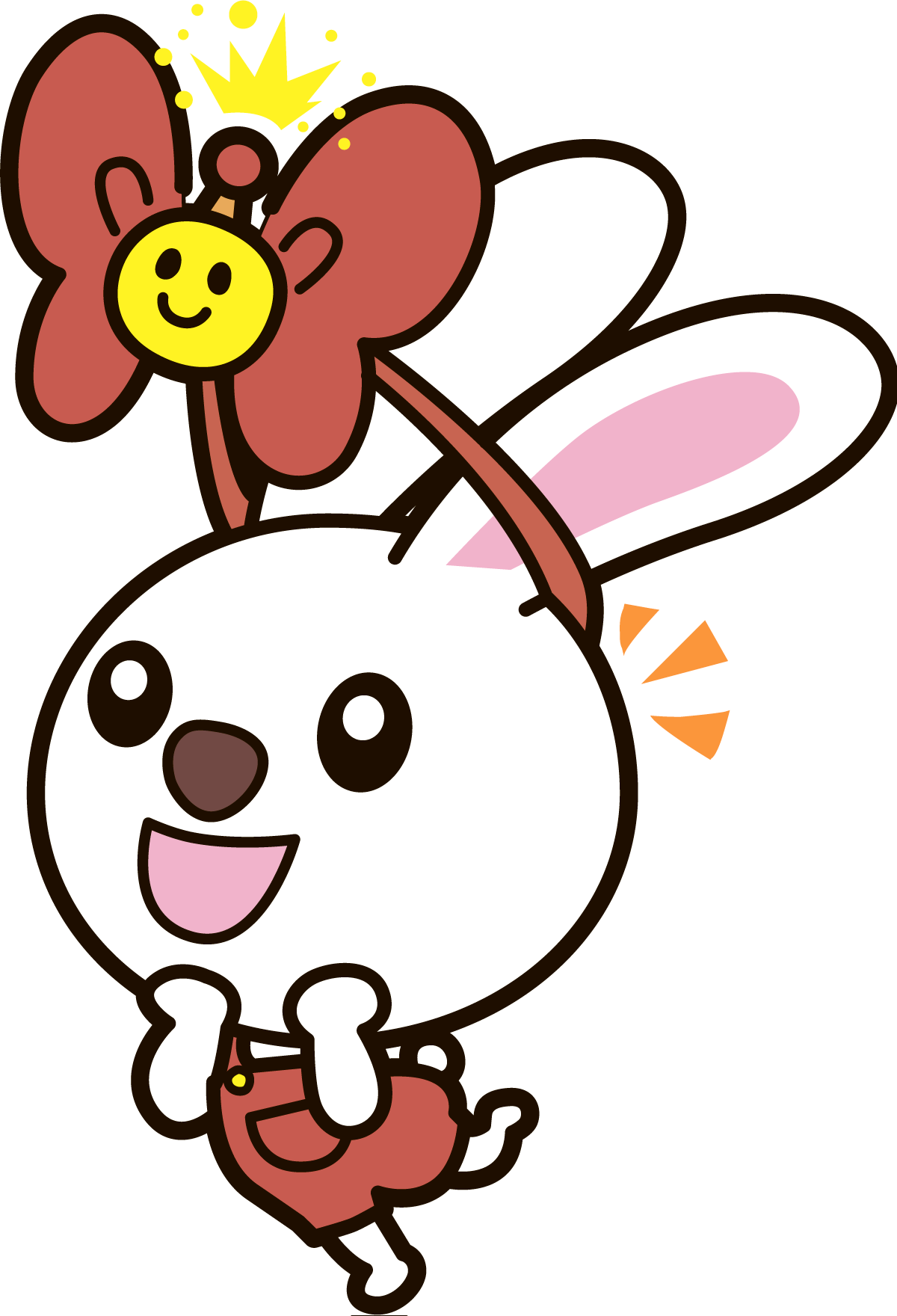天才少女と呼ばれながら、たゆまぬ向上心と前向きな姿勢で類いまれな音楽の才能を開花させた米子市出身のジャズピアニスト、松本茜さん(35)=東京都在住=は、今年でデビュー15年を迎えた。深い〝ジャズ愛〟を胸に自己表現はさらに深化を遂げ、才能ひしめく東京のジャズシーンでもひときわ存在感を放っている。松本さんに15年間の思いや現在の活動、将来の展望などを聞いた。(聞き手は新日本海新聞社境港支社長・岡宏由紀)

―15年を振り返って。
「目先のことをきちんとやろうと思っていたら15年たっていた。具体的にどこかでコンサートしたいとか、誰かと共演したいとか、アメリカ行きたいとかっていう考えがあまりなくて、それより目の前の仕事を100%以上の力を出してやれるコンディションを保つことを第一に考えてきた。どこで演奏するとか、誰とやるというのは、それに付随してくるものだと思う。丁寧に日々を過ごせた15年だったら良かったなと思う」
―20代と30代で違うことは。
「30歳を過ぎてから結構楽になった。20代のころは、なめられないようにしないとと思っていたり。20代前半は事務所に所属していた時期もあったので、どうやって売り出すとかどうやってお金を稼ぐかという話になりがちだった。そうなると、やっぱり見た目とかを求められたり、お客さんも純粋に音楽を楽しんでいる人がどのくらいの割合でいるのかなと思っていた時期もあって。ばかにされないようにしなければとか考えていたけど、30歳を過ぎるとどうでもいいと思ってしまって。聴きに来てもらえるだけでありがたいなと。音楽的にも余裕が出てきて20代より分かることも増えてきて、精神的にも楽になった。若さを求められないから、今がいちばん楽しいかもしれない」
―20代は大変だった。
「年齢が若いということで、ジャズをよく聴いている人に『君の演奏はこうした方がいい』とか『ジャズはもっと激くないと駄目だ』とか、よく言われたりした。若いといいやすいということもあるかもしれないけど、そこで自分のぶれないものを持ち続けるのが結構難しくて、何が正解なのか迷った時期もあった。ただ、自分も次第にジャズの中でもどういうスタイルをもっと掘り下げていきたいのかとか、どういうジャズミュージシャンになりたいのかというのがはっきりしてきたので、誰が何を言ってもいいのかなという心境になってきた」

―事務所辞めて不安は。
「事務所にいた時期は甘えていて、みんなが何とかしてくれるという感覚があったが、1人になった時にどのぐらいやれるか試してみたいなと思って独立した。言われたことをやるより自分でやりたいことを選択できるし、責任感が芽生えた。事務所にいた時はMC(マイクでしゃべるパフォーマンス)もろくにできなかった。共演者の名前を言って曲名を言って終わりという感じだったが、事務所を辞めてからこれはまずいと思った。誰も守ってくれない立場になったときに、MCもちゃんとできないのは甘えだなと思った」
―MCに目覚めた。
「いかにお客さんとの距離を縮めて同じ空間を共有できるかということを考えると、私の場合はしゃべったりする方がお客さんもほっとできるかなと思って。あとジャズファンを増やさないといけないから、やっぱりMCはきちんとやった方がいいかなと思う。とにかくジャズの敷居を下げたい。ジャズファンは若い人が少なくて、漫画と映画の『ブルージャイアント』のおかげで少し若い人のファンも見られるようになったけど、まだまだ年齢層が高い。チャージも高いしなかなか気軽に来れる店も少ないかもしれない。ジャズの知識なくても楽しめるということをなんとかして伝えていきたいけど、それにはMCがいちばんだと思う。でも大阪でMCをすると怖い。『それがオチかい』と言われたこともあって。18歳で東京に出てきて、20代前半のころから聴きに来てくれているお客さんはみんな口をそろえて『MCうまくなったね』と笑いながら言われる」
―演奏スタイルの変化は。
「オスカー・ピーターソンがいちばん好きというのは一貫して変わらない。でもビル・チャーラップに影響を受けていた時期もあるし、ハンク・ジョーンズにめちゃくちゃはまっていた時期もあった。その都度変わっていくというのはあるけど、いろんな人を影響を受けながらオリジナリティーができてくるのではないかと思う」
―どんな演奏をしていきたい。
「ジャズを最初に聞いたときにすごいわくわくした。ジャズってどういう音楽なのか、即興がいつ行われているかも分からなかったけど、楽しいなと思った気持ちはすごく覚えている。ジャズって結構怖いジャズバーのマスターがいて、うんちくを言う常連さんがいて、ジョン・コルトレーン知らないと怒られるイメージがあるけど、そうした知識がなくても楽しく、いい気持ちになるような音楽を演奏したい。生演奏のエネルギーはCDとか配信にはないものなので、生身の人間同士が中身をさらけ出して会話するというエネルギーを感じてもらいたいなと思って演奏している」

―コロナで大変だった。
「当たり前のことができなくなった。毎日人に会って音楽一緒にやってを聴いてもらってということができなくなったのがいちばんつらかった。回りでも気持ちが落ち込んだり、ミュージシャンは社会から必要とされていないんじゃないかと落ち込む人は多かったけど、私は3日で仕方がないかなと思った。シベリアに抑留された祖父が『明けない夜はない』と言っていたけど、祖国に帰られないかもしれない状況でそう言っていたんだろうなと思うと、コロナで騒いではいけないと思った。いかに普通の生活を送りながらクリエイティブでいられるかということを考えたときに、ピアノソロアルバムの制作を思い立った。自宅で気が向いたときにピアノを弾いて、気に入らなかったら全部消して。いいテイクがあったらそれを使うよいな感じで。同時に絵を描くのがすごく好きで、それをジャケットとかライナーノーツに使ってアルバムを制作した。このおかげでコロナがネガティブじゃなかった。毎日充実していた。アルバムのおかげで始めて一人旅とかしたけれど、本当にやってよかったなと思った。昨年東京でもレコ発ライブをやって、いいプロジェクトになったんじゃないかなと思った」
―15年で立ち位置の変化は。
「ジャズ界では35歳はまだ辛うじて若手と呼んでもらえる。40代も若手。50代あたりが中堅。ベテランは60過ぎてから。以前は「茜ちゃん茜ちゃん」といわれていたのが「茜さん茜さん」になった。あ、そうだよねと思った。これから40代はどうしたいか、50代はどうしたいかということを考えながら、例えば生徒さんをどうやって育てていくかとか。CDもいつまで媒体として存在するのかという問題もあり、CDを作ることがだんだん難しい世の中になるかもしれない」
―将来はこういうプレーヤーになりたいというのは。
「毎日進んでいきたいと思う、年を取ると成長速度は落ちるけど、それでも少しずつ前に進んで、ちょっとでも上手になりたいと思う。ただ、大それたイメージが湧かなくて、なんか創造的でいたいとは思う。せっかくアルバムを作ったのでいいスタインウェイがあるサロンとかでコンサートをしてみたなと思う」
―印象に残った出来事は。
「2015年にビル・チャーラップのトリオをやっているベーシストのピーター・ワシントン、ドラムがハービー・ハンコックのバンドにいたジーン・ジャクソンの3人でニューヨークでレコーディングした。ニューオークでの録音は2回目。1回目は事務所の社長といって、楽しかったけど良く分からないうちに終わった。間にミュージシャンじゃない人がいるかいないかでミュージシャン同士の関係性も全然違ってくる。15年は完全にミュージシャンだけだった。2枚目のトリオ・アルバムを2年後に出した。それがが印象的な出来事だった。楽しかったし、いろいろなことを学ぶことができた。ライナーノーツも書いたり、写真もチームで撮ったり。みんなでアイデアを出し合って作ったので楽しかった」
―ジャズをやってきてよかったと思うことは。
「人のつながり。音楽をやってきたことで、ものすごくたくさんの人にお会いしたし、お世話になった。東京に出て15年になるけど、それぐらいやっていると、10年前に聴きましたよという人が久しぶりに聴きに来てくれたりしてうれしい。人と人のつながりって大事だし、心が豊かになる。1回会っただけではそれっきりになる人たちっていっぱいいるけど、繰り返し来てくれる人とか、また聴きたいなと思ってきてくれる人とか、なかなか行けないけど応援しているよという人たちがいるとありがたいなと思う、励みになる。ジャズは自分の中身をさらけ出して演奏するところが魅力的だと思う。それでミュージシャンと共有して、その場にいるお客さんと感動をシェアできるというのがすごく魅力的。音楽をやりながらいろんな人に会えることは、日々の潤いみたいなものを与えてくれると思うし、音楽はやっぱり私のアイデンティティーなので、全てがつながっているかんじがする。続けたらいいことがある。ご褒美みたいなライブもあるし、いろいろな人と出会えるのがいい」

―地元米子でも5月にコンサートをされた。
「愛しかなかった、みんな大好き。本当に優しい。地元では定期的にやらせてもらっていたが、5月の米子公会堂のホワイエでのコンサートがいちばんいい雰囲気だった。お客さんの温かい感じがすごく伝わってきた。地元で演奏できるのがいちばんの幸せかもしれない。好きな場所で好きな人たちがいて、好きな音楽をやって、聴いてもらえて喜んでもらえる。ポジティブな要素しかない」
―過去、日本海新聞のすいヤン「ハロー」に掲載された。
「当時高校生で、よく校長室に呼ばれていた。夜にジャズバーに行ってることがばれてすごい怒られて。担任の先生も音楽に理解がなくて、自分も頭にきていたけど、記事が出たことで知らない先生からも声をかけてもらうようになった。今でも実家の2階のいちばんよく見えるところに記事が飾ってある。両親も喜んでいる」