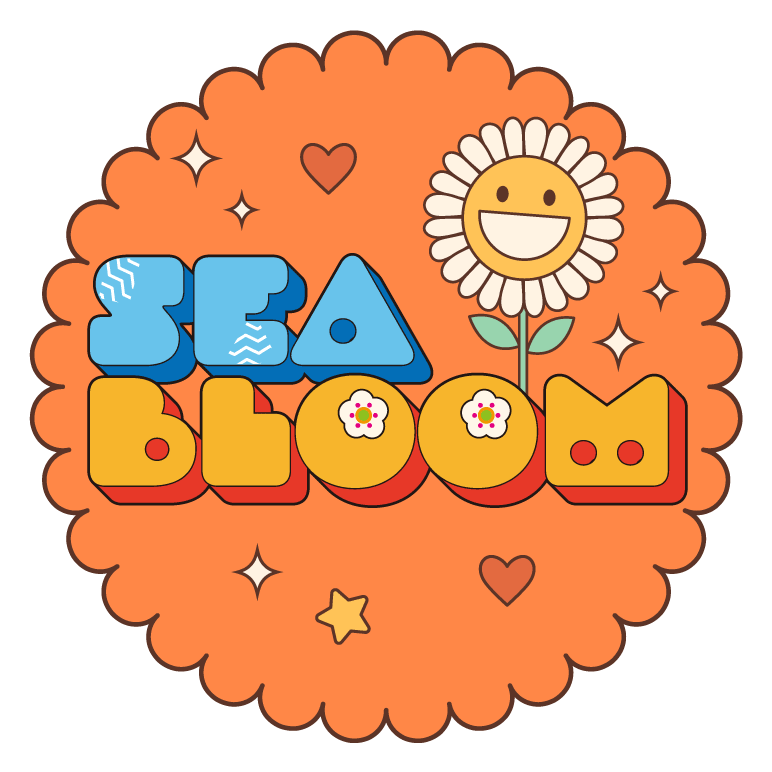詩人や歌人にとって最大の誉れは、名前が残ることより作品が残ること、自分が生み出した詩句が多くの人に愛誦されることではないだろうか。
北原白秋(1885~1942年)はそれに成功した詩人といえるだろう。私は旅先で「この道はいつか来た道」と口ずさんだり「からまつはさびしかりけり。たびゆくはさびしかりけり」と小さな声で言ってみたりすることがある。そのとき、いちいち「これは北原白秋作」だと意識しない。それはすてきなことだと私は思う。
東京都目黒区駒場の日本近代文学館で開かれている「北原白秋生誕140年 白秋万華鏡」(6月14日まで)に足を運んで、白秋の言葉にいかになじんできたか気づいた。
■記憶に刻まれる言葉
本展タイトルの「万華鏡」という言葉は、白秋の詩集「邪宗門」に対する木下杢太郎(1885~1945年)の批評の中に出てくるという。タイトルに用いられたのは、白秋の「輝かしさと瞬時に変化する文学世界」を表す言葉としてふさわしいからだという。
私が感じたのは、多くの人の記憶に刻まれ、時々に喚起されるようなフレーズを創る言葉のセンスである。展示されているのは、詩や短歌、童謡、民謡といったものだ...